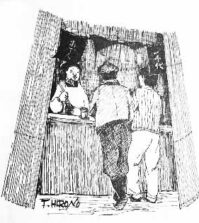ガラス戸の街

窪倉錦次さん(64)。昭和二十年、北支から復員した。父親が待っていてくれた。父は苦労して、人手に渡っていた土地を買い戻し、昔住んでいた同じ場所の野毛の一角に、バラックを建てていた。うれしかった。
野毛の街は一望千里だった。寝そべると、ガラス戸ごしに山手の気象台が見えた。焼けこげの街でも、子供の頃に住んだ場所であり、安堵感が背中からはいあがってきた。
窪倉さんの出征地は、北支といっても、万里の長城をはるかに越えた最前線である。目の前にゴビの砂漠が広がる内蒙古のシルクロードだった。百キロ先に中国軍、そのまた百キロ先にソ連軍が陣どり、終日砂まじりの烈風がたたきつけていた。
騎兵十四連隊といっても、もはや馬では戦線の維持は無理である。トラック部隊であった。終戦までこの地にいたら、生還はむずかしかったろうが、河南作戦に動員となり、洛陽まで下ってきた。そこで急性胃腸炎となり入院。部隊は河南作戦で四分の三が戦死というありさま。間もなく終戦となり、すぐに復員できたのは、奇跡のようなものだった。
もともと窪倉さんの父は、昭和初年から靴の製造と修理を生業としていた。窪倉さん自身も、学校を出る頃には靴づくりをマスターしていた。出征し、初年兵教育が終わると、特技を認められて、銃を取るよりも、軍靴の修理をする毎日であり、他の二人の見習いに仕事を教えていた。
復員の疲れもいえて、父と二人での靴屋が再開し、昭和二十四年に、窪倉さんはおない年のチヨコさんと結婚した。しかし、物質不足は、皮が自由化になるまで続く。月に三足ぐらい作る程度の皮の配給しかない。お客はどこかで手に入れた皮を持って来店する。おおかた、米軍の横流し品であったと思われた。靴は高嶺の花となっていた。
十歳ぐらいの子を頭に、五歳ぐらいまでの五人連れの浮浪児がいた。いつの間にか店の中に来て、窪倉さんの仕事をのぞいている。「お水をちょうだい」などといいながら入って来る。窪倉さん夫婦はなかなか子供ができなかったので、この子たちがいつも気がかりだった。
ある日、連中はみな、足に新聞紙を巻きつけていた。「こうするとあったかいよ」。
夫婦は涙がこぼれそうになった。「もう少しガマンしなさい。材料が来たら、その小さい足にピッタリの靴を作ってあげるよ」。窪倉さんは心の中で叫んだ。
もう一人、いつもウインドーの運動靴をみつめている子がいた。目が合うと行ってしまう。「あなた、今度来たら、あの子に運動靴をあげましょう」。「ああ、そうしよう。でも、自尊心の強い子のようだから、注意して話しかけなければね」。それっきり、その子は来なくなってしまった。
五人連れもいつの間にか消えてしまった。「親はなくとも子は育つ」。ぜひともそうあって欲しい。それが二人の気持ちである。
昭和三十年頃から、東京オリンピックまでが「橘屋靴店」の最盛期だった。朝八時から夜九時まで、日曜も祝日もない生活がくり返されたが、靴底の合成品が出回り始めると、パッタリと仕事はなくなった。
今、窪倉さんはサラリーマンになった。しかし、ていねいな修理を見込まれ、まだまだ訪れる客は多い。店の表戸は閉めてあるが、時々仕事をしなければならない。修理台に向かうと、焼けた街や、砂漠や、ボロをまとった子供たちが、ガラス戸のむこうから、いつも見つめている。
 野毛ストーリーより
野毛ストーリーより