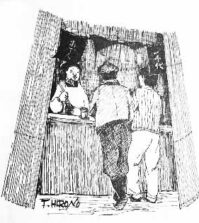駅馬車

浦山桐郎、永田雅一、オーソン・ウエルズ、並べて書いてしまっては、見識のなさを笑われるかも知れない。三人は、映画を作る側の人である。この一ヵ月の間に、相ついで亡くなってしまった。どう考えても、一つの時代が終わりつつある。
荒木幹男さん(52)は、映画を見せる側の人間である。自分を「活動屋」という。青春の頃から顔が変わっていないような人。野毛の映画館「かもめ座」主人。
その半生は、上映映画を選ぶことについやされた。だが、これからの映画はどうなってゆくのか。頭の中には、幹男さん自身の人生をも積み込んだ「駅馬車」が、次のステーションに向かって走り続けている。
「かもめ座」は、昭和二十七年十一月に開館した。マッカーサー劇場の持ち主であった平古寿次氏が、その姉妹館として、当時としてはぜいたくざんまいな作り方をした。館名も一般公募で決めた。映画がこれから伸びてゆく華やかな時代だった。
こけら落としは、上映を待たれながら引く手あまたで、封切館が決まらずにいた「風と共に去りぬ」だった。まずは、満帆のスタートであった。
翌二十八年、平古さんは「かもわ墓」を手放し、幹男さんの父、逸雄さんが経営者となった。逸雄さんの路線は「名画劇場」だった。「道」「自転車泥棒」といった名作が並んだ。その頃、幹男さんは大学生であり、父を手伝って、フィルムの借り入れの仕事をしていた。
昭和三十年代は、映画の全盛期だった。まるで雨後のタケノコのように映画館が誕生した。伊勢佐木町にあったグリーン・ホールなどは、映画好きが高じた野毛の中華料理店「日清楼」のご主人が作ったものだった。
幹男さんは、大学を卒業してから一時期、違う仕事をしていたが、三十三年から本格的に「かもめ座」を職場とした。張りのある毎日だった。劇場に置かれたアンケート箱には、上映希望映画のカードが、いつもギッシリとつまっていた。客は帰りしなに、「○○はいつ頃上映するの」と聞いてくる。
映画館にはランクがあり、伊勢佐木町にピカデリーができてからはそれ以前に上映はできない。「いついつ頃になるでしょう」。「そうか、来るまで待ってるからな」。そんな具合なので、作品の借り入れにも熱が入った。
その頃から、これは町のニーズともいえると思うが、ジョン・フォードの人情活劇の要望が高く、「長い灰色の線」「静かなる男」という路線になった。
港湾関係の作業員というと、ガサツな連中を想像するが、客の中に英語がペラペラで、映画の原題がポンポン出てくる男がいた。帰りにしみじみとした感想をいってくれる。幹男さんは、その後姿を見送りながら、どんな人生を送っているのか知らないが、本当に映画は万人のためにある、と確信した。
昭和三十四年、皇太子さまご成婚をきっかけにテレビが普及した。しかし、幹男さんの敵はテレビではない。映画の製作本数の激減と客の気質が、映画を他のひまつぶし娯楽と同一視する、そのことにある。年間に百六十本を必要とする三本立てはとうにむりとなり、二本立てにしても、意に添わない物を上映しなければ追いつかない昨今である。片手間の映画館は、すべて転業してしまった。
今、幹男さんを乗せた駅馬車は、映谷の危険な場所を疾走している。ここを切り抜ければ録の平原がある。襲いくるインディアン。やがて聞こえる騎兵隊のラッパガンバレ、「かもめ座」! END。
 野毛ストーリーより
野毛ストーリーより