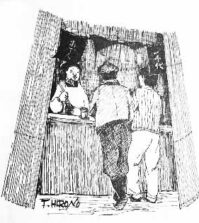炎の中で

小川キヨさん(86)。明治三十一年、野毛に生まれた。今では知る人も少ないが、野毛で生まれた現在五十歳代の人は、だれもがこの人の手をわずらわせている。五十年にもわたって、野毛で助産婦さんをしていたからである。
キヨさんの生まれたころの野毛といえば、野毛山から都橋にかけて、月に二度、お不動様の縁日のにぎわいが見られるような時代だった。出船入船にあけくれる、古き良き時代である。
キヨさんの父親は、明治十年ごろから、「小川海員紹介所」を経営し、東洋汽船や山下汽船などに船員をあっせんしていた。この会社は昭和十年ごろまで続くのだが、若いころのキヨさんは、父の仕事の手伝いで、上海や香港にたびたび事務連絡に出かけた。そうした機会を通じて見聞を広げ、当時としては珍しく「女性と職業」について考えていた。
あっせん業では、いつまでたっても手に職がつかない。女性の職業といえば、当時は看護婦か助産婦である。十八歳のころ、十全病院で看護婦として働きながら、桜林助産婦学校に学び、助産婦免許を取得した。
昭和二十年五月二十九日、「横浜大空襲」である。何があろうと、一歩も野毛を動こうとは思わなかったキヨさんだが、この日の空襲はいつもとは少しばかり違っていた。爆発音がなく、シュルシュルという落下音がすると、突然、ポッというさく裂音とともに、そこら一帯が一度に燃えあがった。川までが燃えていた。これでは、キヨさんがいくらあがいても、生まれ育った家を守りぬくことなど不可能だった。
炎にまかれながら、檀家寺である山元町の浄光寺へ逃げた。浄光寺は、周囲に立ち木があったので、まだ健在だった。キヨさんが縁の下に飛び込むやいなや、「おーい、お産婆さんが来たぞ」という叫び声。ひきずられるように奥に入ると、もう、すぐにも産まれそうな女性がいた。
「た、たすかりました。お願いします」。泣きながら手を握りしめられたキヨさんは空襲のことなど、瞬時に頭から吹き飛んだ。「だれか、やわらかい衣類をお持ちの人は、ここに出してください。それからフロの残り湯でもいいから運んでください」
火の粉の舞う下で、消火ならぬ、新しい命のためのバケツリレーが行われた。一人が出産すると、それに誘われたように、また一人、キヨさんを呼ぶ声がかかり、結局、三人をとりあげた。
バケツ運びの一人が、「もう、ここもダメかもしれねえ」といったとき、今、命をさずかった赤ん坊を思って、キヨさんの涙は、とどめようもなかった。しかし、腹の下にあまたの命を抱え込んだ浄光寺は、空の崩れるような地獄をみごと耐えぬき、焼け残った。
結婚をしなかったキヨさんは、天涯孤独である。十年前に助産婦は廃業した。今は体も弱ってしまった。キヨさんがとり上げて、小さいころ、かわいがった鮨の「かめや」の小野三男さんの妹、照代さんが養女となっている。照代さんは結婚して、「平島」姓になったが、キヨさんのもとを離れようとはしない。子供のころの思い出に、毎日、恩返しをしているような照代さんの明るい顔に、キヨさんの生活は委ねられている。
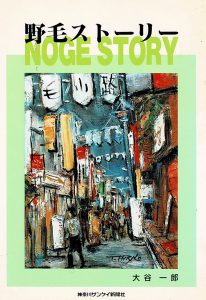 野毛ストーリーより
野毛ストーリーより