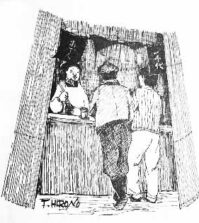二等兵物語 (大谷一郎)

桜木町駅前の「ぴおシティ」の地下にある立ち飲み屋「石松」。野毛にも同じ名前の店があり、ともどもその安直さではやっている。
この飲み屋の前身が、果物屋、だというと、何だかわけがわからなくなるが、その「フルーツタミヤ」が開店したのは、焼け跡に桜川が流れていた昭和二十二年八月のことだった。
早乙女民一さん(68)。前年の二十一年六月に、戦地から帰国した。「日本へ生きて帰れてうれしかった」というが、この人には別のわけがあった。戦争が激しくなろうがなるまいが、「帰るに帰れない」、もうひとつの理由があったからである。昭和十三年に召集され、十六年に満期除隊となった。除隊したときは、星二つの一等兵。三年もいて一等兵というのは、あまり聞いたことがない。最低でも星三つの上等兵になっていなければ、とても田舎に帰れない。同僚が帰国してゆく中で、早乙女さんは、帰国を断念した。
どうしてそんなに昇進が遅かったかのか。ひとことでいえば、軍隊のペースにどうしもあわなかったのである。
酒が好きで、よくよその班まで出かけてかくれ飲みをしていたが、点呼の頃になり、あわてて帰る時、ズボンを置いてきてしまうなどの失敗は枚挙にいとまがない。いくら怒られても、ワザとやっているのではないから、やめようがない。
それでいて、明るくて人に好かれる性格は、いつの間にか軍隊のワクを大きくはみ出してしまう。こうなると、もう怒る者もなくなり、一転して、たいへんすごしやすい毎日となった。
除隊後、軍属として残してもらい、相変わらず気楽に暮らしていたら、敗戦となった。死ぬような思いはしたが、何とか帰国できた。
横浜は焦土と化していたが、栃木の実家は無事だった。しかし、田舎にいても仕事がないので、また横浜に帰って来る途中、引き揚げ手当として貰った”虎の子”の三千円をすられてしまった。
さすがにこの時は、目の前が真っ暗になったが、実家に頼み込んで八千円の借金をし、「横浜協進産業果実部」という看板をあげた。ここからまた、早乙女さんには何の苦労もなくなった。
初めのうちこそ、米軍のバナナの払い下げのセリに出たりもしたが、そのうち品物がむこうからやって来るようになった。持ち込むのは、ほとんどが中国人である。彼らは自由に米軍の「PX」で買い物ができる。それにプレミアムをつけて、大量ではないが、二日おきぐらいに持って来る。
レモン、チョコレート、ケーキ、その他食料品一般…。PXから出た品物だから、店頭に並べるわけにはいかない。奥の方にしまい込む。店に出ているのは、リンゴぐらいなものである。それなのに、どういうわけか、客の方が知っていて、勝手に注文する。リンゴを見ながら、「レモンはない?」「今日は、チョコレートは・・・」。すると、早乙女さんは奥の方から、注文の品をゴソゴソと持出して来る。
もう、ただ座っているだけでよかった。品物が勝手に持ち込まれ、それが飛ぶように売れてゆく。労働者の日当が二百四十円の時代に、毎日の儲けが二千円以上にもなった。
これで気がヘンにならない方がどうかしている。三日に一度はキャバレーにくり出す。「もう、ずっと死ぬまでこのまま行けると思ってたんだよ。アハハハ」。当時を思いだして早乙女さんは笑う。「ごしの銭はもたない」などと気取りはしなかったが、暮らしはこんなペースで続いていった。
 野毛ストーリーより
野毛ストーリーより