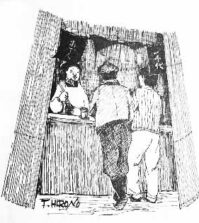消えゆくヨコハマの闇の中で (渡辺光次)

老朽化のあまり錆びつき、朽ち果ててはいるが、 威風堂々たるそれらの建物や空間は、魔力を持った生き物のように、 この港町の全盛期時代の記憶とそのエネルギーを静かに物語っていた。
八十二年三月三十一日、本牧米軍基地が返還された。 「戦後四十三年間、中区の中心部の接収に終止符が打たれ、ヨコハマは基地の街を脱皮しようとしていた。
ちょうどその二年前、緑区に住みながら横浜のこと を何も知らないぼくは、ただ雑誌を作る仕事がしたいという理由で『浜っ子』というタウン誌に勤めた。そ してこの年の初め、編集の責任を任されたばかりだった。
緑区のニュータウンは、緑の芝生を持つ一戸建ての 住宅地群と駅前のハンバーガーショップ、そしてカラ ルなファッションビルの立ち並ぶ画一化された街だった。すべてが真新しいそこは、表面的で薄っぺらな イメージばかりが目についた。
しかし田園都市線から横浜線に乗り換え、編集部の ある中区松影町に向かうにつれ、あたりは次第にモノクロームの荒廃した風景に変わっていった。当時の港 周辺部には、至る所に巨大な「闇の世界」が広がっていた。
本牧米軍住宅地、三菱ドック、赤煉瓦倉庫、新港埠 頭、本牧埠頭、桜木町高架線下、大黒埠頭…。
老朽化のあまり錆びつき、朽ち果ててはいるが威風 堂々たるそれらの建物や空間は、魔力を持った生き物のように、この港町の全盛期時代の記憶とそのエネルギーを静かに物語っていた。
ヨコハマは小さな町だった。中区、西区そして南区 と磯子区の一部で、少しでもその外に出ると、緑区の ようなニュータウンの開発工事に出くわした。それだ けに街に住む人々の結束は固く、「闇の世界」を背景に 活力あふれた活動が生まれた。
暗くうす汚れた壁が続く桜木町高架線下には、落書 きアートが延々と描か れ、中村川では、古いはしけを 劇場にした演劇活動が注目を集め始めた。港の倉庫を 芸術活動の拠点にしようという動きや、そこを舞台にしたアウトロー映画のファンたちが、独自の選択眼で 「ヨコハマ映画祭」を始めた。また米軍基地のある本 牧では、市内のジャズ ファンらの手作りによる「本牧 ジャズ祭」も始まった。
そしてノースピアや本牧にある古ぼけた外国人向け バーは、一躍若者たちの人気スポットになった。
当時の横浜は、全国的な注目を集めるユニークな文化の発信地だった。
建物や都市空間の闇に潜んださまざまな記憶が、その時代に生きる人間たちに一種のインスピレーションを与え、ヨコハマの街が再生してゆくようだった。
そして、ヨコハマの闇を満た ていったクリエイティブな想像力は、同時に、街を壊しては造り、また壊 にしては造るというバカバカしい都市開発への強烈なアンチテーゼでもあった。
八十三年二月、こうした闇に息づくエネルギーの再生 を突然断ち切るような、後味の悪い事件が起きた。港周辺に寝泊まりする浮浪者たちが何者かによって次々と襲われたのである。犯人がわからないまま約一 か月間、犠牲者が増え続け、死者まで出たのである。
浮浪者として殺された須藤泰造さんは、偶然にも友人のカメラマンが頼み込んで自分の写真のモデルにな ってもらった人だった。「浮浪者の死として簡単に片づけて欲しくない--。多くの人に須藤さんを知ってほしい。決して特殊な人間なんかではない」と友人は、 文何点かの作品と一緒に話した時のテープを持って、編集部を訪ねてくれた。それは、ヨコハマの闇が語り出 した声のようでもあった。
須藤さんは青森の故郷を離れ、日雇い労務者として 東京を経て、横浜の寿町へ働きに来ていた。故郷で米屋を営んでいたが、ある年末、例年にない多くの注文をこなさねばならなくなり、奥さんに無理をしいるあ まり、寒さと過労で死なせてしまったのだ。以来、単身故郷を離れ、労務者としての生活を始めた須藤さん は、ぜんそくなどの持病を抑えながらも仕事を続けて きた。しかしこの仕事は年齢が六十にもなると働きたくても仕事がもらえなくなる。仕事がなくなると体力 も急速に衰え、行くところもなく、この公園に寝泊ま りするようになったという。
須藤さんが、山下公園を選んだのは、明け方、大桟橋の先端から眺められる日の出を楽しみにしていたからだ。「最初はちいーさくて、赤くなって、ちょうど1 日月みたいに出てきてね。だんだん大きくなってい でしょ。五分か、そこらの時間だけどね。昇りきる てはね。すごくいいですよ」と録音テープの中でうれしそうに語る須藤さんは、山下公園で新たな人生を歩もうとしていた矢先に、その命を一方的に絶たれてし まった。
逮捕されたのは、南区に住む中学生のグループだっ た。彼らは、街をきれいにするために襲撃したと悪び れず話したという。
同じ年の十一月、三菱ドックの取り壊し工事が始ま った。役に立たなくなった造船工場は、二十一世紀の オフィス空間に変貌する計画だった。
ブルドーザーやパワーショベルの機械音が街中に響 き始めた。本牧米軍基地の各施設も、埃と轟音の中で 壊され、大地から引きはがされ、その土地も深く掘り 起こされた。ここには高級ニュータウンが建設される 予定だった。そして、大黒埠頭でも、本牧埠頭でもヨコハマのいたるところで同じ轟音が鳴り響き始めた。
都市計画では、用済になった建物は、廃墟に過ぎない。廃墟は、新たなる用をなすものに根こそぎ取り替 えられる。そして、街の片隅にひっそりと生きる生命や、街に息づく創造力すらも、用をなさないものとし て葬り去ってしまうのだ。
須藤さんの事件以来、山下公園に棲む何人かの人達 と知り合いになった。中でも須藤さんの親友だった水井徳次郎さんは、堂々たる風格のある人だった。須藤 さんが亡くなったあと、行政は港周辺の路上生活者ら を施設などへ収容しようと働きかけたが、永井さんだ けは、「俺はこのとおり見てのルンペンだ。でも乞食で はないんだ。人を頼って生きているのが乞食だ。俺は ルンペンだ」といい、頑として公園を動こうとしなか った。
八十四年一月、そんな永井さんも、横浜に十五年ぶり の大雪が降った日の明け方、真っ白に覆われた雪の中 で、凍死しているのを発見された。七十一歳だった。 (永井さんのことは、作家の佐江衆一氏の『横浜ストリートライフ』(新潮社)に詳しく書かれている)
永井さんこそ、このヨコハマのなかで自分の生き方 を貫いた人だった。永井さんは、ヨコハマの闇が雪の 白さに覆われてゆくように、堂々とたくましく死んでいったのである。
永井さんを特集した号を配本し、編集部に戻った時、 定期購読者のあるホテルから電話がかかった。配本された四十冊すべてを廃棄処分にしたという。そしてぼくは責任者として呼び出された。その支配人は永井さんの写真を指さし、「こんな社会の敗北者 をウチの客に見せられるわけがないだろ」と怒鳴り散 らした。
街の中に鳴り響いていた開発工事の轟音がひとつ静 まるたび、ヨコハマの闇もひとつずつ消え、ヨコハマ は、どこにでもあるような、良識的な顔をした街にな っていた。
八十四年には、港周辺を周遊する二階建て観光バス・ ーラインが運行を開始。開発の進む金沢の郊外住 シーサイドラインという新都市交通が着工した。
ニュータウンと市内の中心部が次第に接続され ていった。 さらに翌年には、桜木町駅前に帆船日本丸が一般公開され、横浜駅東口には世界最大級のフロア面積とい うふれこみで横浜そごうがオープンした。山下公園通りにはガス灯が復活し、そこに面したビルの一角にFM横浜が開局した。みなとみらい地区では、横浜市 美術館の建設工事が着工した。ヨコハマは完全にあの 画一的なニュータウンの顔に整っていった。ぼくがタウン誌をやめたのは、この年の初夏のころだった。

ハマ野毛第5号 (1993.9.10)より