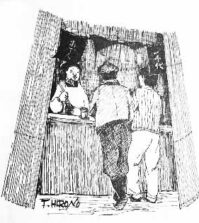調理上の唄(2) (大谷一郎)

敗戦。
焼けただれた街で、関内のレストラン 「キムラ」のご主人、貴邑富士太郎さんは、遺体 の処理をする明け暮れであった。
そんな中にあっても、富士太郎さんは、心のす みで理想の料理を考えている。焼け跡に座り込ん でながめる作業で汚れた手のひらには、いつしか、 自分の料理を囲んで談笑する人々が浮かんでいた。
昭和二十四年三月、街の復興に活を入れるべく、 反町公園で、日本貿易博覧会が開かれた。それに 従事する市職員と議員用に、折り詰めの注文があった。すべてが統制の時代であり、材料の入手は 不可能に近かった。
が、何とか工面するしかない。時代も落ちつく方向にあった。どこか、便利なところに拠点を。 昭和二十四年、借金をして野毛に「キムラ」を再開した。しかし、主食は統制で、まだ売れない。 戦後初めて売ったのはしょうちゅうに砂糖、ショウガ汁を加え炭酸で割ったサワーのような飲み物とつまみだった。
驚いたのは、この辺が「泥棒横丁」といわれて いたことだった。いきなり店に飛び込んできて、 裏口へ走り抜けるヤツがいる。それを追って、も う一人が、「ドロボー」と駆け抜ける。
強烈なインフレと極度の生活困窮。しかし、い ままで長い間押さえ込まれてきた自由がそこら中 からわき上がり、人間性の復活が人々の魂をゆさ ぶっている、そんな時代だった。
一片の野菜にも工夫をこらす富士太郎さんの料理は、材料入手との闘いだった。独特な調理法を 編み出しても、秘密にしない。みんなに教えてし まう。食べてもらって反応を見て、また次の料理 を考えてゆく。そんなところが、人の輪を広げてゆく。
「河童会」という集まりがあった。動物作家の 戸川幸夫さんたちが、料理に舌つづみを打ちなが ら奔放な夢を語り合っていた。
ある日、見知らぬ女性が来た。生麦の「貝駒」 の妹さんだった。貝駒は復員していた。しかし、 重いマラリアをしょって帰って来た。しばらく妹 さんが商売に来ることになった。
昭和二十五年、朝鮮戦争。富士太郎さんの長男は医者、二男は関内の昔の店の近くにレストラン「イータリーキムラ」を出店した。 すべてが好転してゆく。そんな時、いきなり不幸が富士太郎さん夫婦を襲った。昭和四十四年、 横浜市大で外科医をしていた長男健司さんの急死 である。三十二歳だった。富士太郎さんはぼう然自失した。
三男の悟さんは、この時サラリーマンをや めた。このままでは父親は、自分を投げ出しかね ない。それほどの深い悲しみを父親から感じたか らである。
十年の歳月が流れた。野毛の祭り。元気にな った貝駒が「山車」の上で太鼓をたたいている。 富士太郎さんも元気だが、すっかり銀髪となった。 そして、調理場の唄は、悟さんによって歌いつがれてゆく。
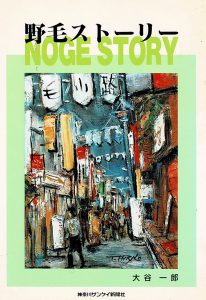 野毛ストーリーより
野毛ストーリーより