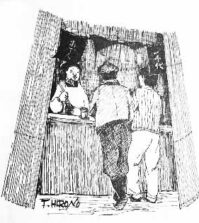根岸家 -ぺージェントの化石- (大内順)
 photo by ROBERT HUFFSTUTTER
photo by ROBERT HUFFSTUTTER
人間と同じように町にも青春の時代があるのかもしれない。
人間と同じように町も夢を見ることがあるのではないだろうか。
そして、ヨコハマという町がみたとびきり綺美な夢が、あの「根岸家」という店だったのではないか。
何年前のことになるだろうか。
野毛小路の「パパジョン」の、駅側の隣りにその頃あった居酒屋「やまぶき」のカウンターでとなりあわせに坐った年配のガイジンと、酔いの勢いにまかせてお互い滅茶苦茶なブロークンでトンチンカンな話をしていたとき、しきりに「ニギシャ、ニギシャ」と言うのがどうにも判らず、でもどうやら店の名前のようで、イントネーションからはどうしても「リキシャ、リキシャ」と聞こえてしまうのだった。ならば「人力車」のことか。それなら、本牧・小港の「リキシャルーム」のことをいっているのかなとおもっていたら、これがよくきいてみるとその男は「ネギシヤ、ネギシヤ」といっているつもりのようだった。
すると、記憶のうんと底から、何とも古くさい一軒の酒場の残像が浮かび上がってきて、ぼくはなんだかとてもいい気分の酔いのなかへ入っていけそうな気がした。
「根岸家」だったら勿論知っているとも。
そのコンテナ船の船員だというオランダ人と「お国のレーベンブロイはベリー旨い、大好きだ」、「ノー、レーベンブロイはドイツである。ネーデルラントはハイネケンであるぞよ」などとたわいないどうでもいい会話を延々と続けながら、ぼくはネギシヤというコトバを口にするたび、その響きの快さが、なんだか無性に嬉しかったのだった。
「あー、この人も根岸屋で飲んだんだ」
土地っ子以外にはもう知る人も少なくなってしまった其処、「根岸家」。
磯子の埠頭から根岸線に乗ってやってきたその初老のオランダ人船員は、昔来たことのある根岸家を探しているうちに野毛に迷いこんだものらしかった。
だけどいくら横浜中さがしてもその店を発見するのは無理というものさっ。何故なら根岸家はとうの昔に廃業してしまっているのだから。
昭和五十五年九月九日付朝日新聞の横浜版。東京商工リサーチ横浜支社調べ「八月分倒産状況」の記事の中に「大衆酒場根岸家本店」の名が見える。負債額は三億円。
そうか、あの店が無くなって、もうそんなに経つのか。
「根岸家」、そこは居酒屋(もちろんそうだが)という言葉ではなんとも説明しきれないような全く変な店だった。
場所は伊勢佐木町の四丁目。関内・吉田橋から行くならオデヲンの交差点を渡って真っすぐ、二本目を右折してすぐの左側。今は駐車場になりているだだっ広い空き地。そこの乎前半分を使って根岸家はあった(もっと昔こはそこの駐車場全体が根岸家だった時代もあったらしい)。
枝ぶりの悪い松の木と貧相な植え込みがある。黒い瓦屋根。漆喰の壁に「インターナショナルレストラン」のネオン。
左側にある煙草売り場をかすめて、雨天体操場のような広い店内に入る。天井に提灯の列。季節はずれの
桜の造花がゆれる。両すくみの谷間のようなビニールレザーのソファーに沈みこむとありとあらゆる職種の人たちの話し声、歌う声、独り言、楽団の音楽などが混然と混じりあってワンとした店内にあふれる音の沸騰に巻き込まれる。
酔いどれたちの頭越しに「イラッシャーイ」という塩っからい声が流れていく。片腕のない用心棒の日高さんのすがれた声。今でいえば野毛の叶家の喧噪の隙間から時々聞こえてくる「ヘーイ、銘酒イッチョー」の声(高橋さんの)によく似た、港の潮風で一度潰してから酒でゆっくり磨きあげてきたようなアクの強い暖れ声。
割烹着を着た大勢の仲居たちが、分別をわざと無くしてしまおうとしている酔っ払かのアラクレ相手に、世辞を言ったり叱り付けたりしながら酌をしている。
ノスタルジーのアナルキズム。
酒の種類は何でもあった。菰被り(こもかぶり)がデーンとあった、勿論生ビールがあった、バーテンダーの後ろにはあらゆる洋酒の瓶が逢か彼方まで続いていた、ブームなんてもの(ケッ、くだらない)になる前の焼酎があった、朝鮮の酒があった、中国の酒があった、要するに世界中の酒があった。
寿司があった、天麹羅があった、焼き鳥があった、そばがあった、うどんがあった、カレーライスがあった、どんな丼でもあった、中華があった、洋食があったなんでもあった、お汁粉はどうだったかしらないが(あったかもしれない)、雑煮は確かにあった。ぼくは覚えていないけど、食べた人がいる。この雑誌の加藤桂さんの文章に挿絵をかいてくださっている画家の片山健さんがその人だ。片山さんは中華街で島尾敏雄さんと食事されたあとに種村季弘さんや西岡武良さんや堀切直人さん達と一緒に根岸家に寄って、まわり中、目の坐ったおっかない酔っ払い達にとり囲まれながら小さくなって生玉子入り(!)のお雑煮を召し上がった(酒が苦手だから)。だから断じて雑煮はあった。安部川餅のことは俺は知らびい。磯辺焼きについても責任はもてない。だけどお雑煮だけは絶対にあった(なにをムキになっているんだか)。
箸でスパゲティーーを食べている。
フォークで天麹羅そばを食べている。
言い争う声が聞える。あちこちで喧嘩が始まる。早すぎもせず遅すぎもせぬ、後に怨みが残らないような絶妙のタイミングで用心棒が仲裁に割って入る。
根岸家は、そんな店だった。
黒澤明の昭和三十八年の作品「天国と地獄」のなかに当時の根岸家がでてくる場面がある。あまりにも有名な映画だからマニアならずともご覧になったかたも多いとおもう。
誘拐事件のストーリーである。犯人は実業家の息子を誘拐するつもりで、間違って住み込みの自家用運転手の息子を誘拐してしまう。警察が横浜の高台にある邸宅に逆探知装置を準備して、犯人からの電話連絡を待つ。
その壁一面のガラス張りのサロンから見渡せる遥か下界の街のパノラマ。遠くに三菱ドッグの巨大なクレーンが林立している。その手前にごたごたと踏みつぶされたようにひろがっている横浜の街。
その中のどこかに犯人がいる。その中のどこかからか、望遠鏡で山の上の家を見上げている。
三船敏郎扮する実業家は、他人の子供の身代金として三千万円を払わなくてはならない。しかし、その金は自分の実業家生命のすべてがかかっているどうしても出すに出せない金なのだ。それを払えば無一物になってしまう。すなわち天国から地獄へまっ逆さまというわけだ。そしてその西区浅間台の山の上(今、浅間台小学校がたっているところ)にそびえる豪邸が天国だから、〈眼下に拡がるゴミゴミしたスラム街、長屋と路地、黄金町ガード、モルヒネやヒロ尹ン中毒患者と売人達、港湾労働者と売春婦、そんな全部が地獄。もちろん根岸家は地獄の側にある。
そして確かにそんなものの集大成が根岸家だった。
追い詰めた誘拐犯人を尾行している刑事達。それぞれが船員、サラリーマン、愚連隊のあんちやん、沖仲士、浮浪者、売人、遊び人、華僑などに変装している。
根岸家に入っていく犯人。尾行する刑事達もつづいてそっと潜り込む。
ロックンロールが鳴り響いている。広い店内に蠢く、そこにいるのはそんな人、人、人。そのなかで刑事達が変装できないのは売春婦や夜の女たち、紅毛碧眼の船員、縮毛漆肌の黒人、ベトナム戦線から帰休中のGI、つまり女と外国人。そんな女と外国人の客もたくさん根岸家に来た。
根岸家を知っている野毛の人たちと、あの店の思い出話をしていると、必ず微妙な細部にズレが現れる。
(はたして、瓦屋根だったのかトタン屋根だっなのか)そして皆譲ろうとはしない。それはお互い、通った時期が違うということなのか。しかし一人一人がそれぞれの「自分だけの根岸家」を大切なかけがえのないものと考えているのではあるまいか。
そして気がつくと、いつの間にか彼等は皆一様に目を細め遥か遠くをながめているような目つきになってしまっているのは何故なのだろう。みんなはあの店を透り抜けた彼方の一体なにを視つめているのだろうか。
グッドーオールドーデイズ。
もう一度あの時のあの場所のあの空気を吸ってみたい。
別に、今の暮しにとりたてて不満があるわけではないけれど・…
親不孝通りからダンスホールが無くなっていない、だから親不孝通りが消えていない。真金町遊廓は閉鎖されていないし、本牧ベースはまだ座間へ移転していない。コンテナ船はまだないから、マドロスも沖仲士も不要ではない。横浜はまだ無感情な人工装置としての都市ではない。だから「根岸家」という雑音は目障りではない。
人間と同じように町にも青春の時代があるのかもしれない。
人間と同じように町も夢をみることがあるのではないのだろうか。
そして、ヨコハマという町がみたとびきり綺美な夢があの「根岸家」という店だったのではないか。
閉店した根岸家は、それからしばらく頽老の姿を町に晒していたが、やがて無人の店内から不審火を出し、古い乾ききった木造のその店はあっというまに燃え尽きて消え去った。
つけ火だったらしい、といううわさが土地っ子のあいだにひとしきり飛び交った。
そして、その夕まぐれの火事の炎のなかに、理想とも希望とも関係のない聖っぽいけどのんびりしていた横浜の町に君臨していた、「戦後」という残照の最後の輝きが、消えた。