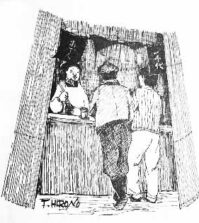魚河岸に歌が・・・ (大谷一郎)
昭和二十一・二年。
横浜は大空襲により、灰塵と帰し、わずかに焼け残ったビルには、星条旗かはためき、関内の空には、占領軍のオートジャイロか爆音をたてて昇り降りしていた。食糧事情は最悪。日に二、三人の餓死者が出る。連日の「米よこせ」デモは暴動寸前であった。
そんな中で、野毛は再生の声をあげる。その街を踏み台にして、一人の少女が通り過ぎて行った。
魚河岸に歌が流れる。
「やあ、来てるじやねえか。ちょっくら聞いていくか」
青木橋の交差点を海に向かうと横浜中央市場がある。朝八時ごろ、魚を入れる「ダンベ」という杉板の箱を積んで、リヤカーやくろかね号、ダイハツ三輪などか集まってくる。
商売が始まるまで、通称『茶屋』という小屋の前かたまり場となる。そこに特設ステージかできる。「ダンペ」を積み上げるのである。縦七十五センチ、横四十五センチ、厚さ十五センチほどの箱を五、四、三、二、一と積んでゆけば、子供の足でも登り降りできる階段ステージとなる。その舞台で少女が歌っていた。
野毛で「だるま鮨」をやっている山本俊一さん(吾一)も歌を聞いていた一人である。
「いやあ、とにかくウマイもんだったね。魚増の娘だってことは知ってたけど、もうみんな″美空ひばり″と呼んでたよ。本人もそういっていたし。まだ小学校前じゃなかったかなあ」
「美空ひばり」
磯子区滝頭のマーケット内の「魚増」の長女として生まれる。戦争は激しくなり、父親も召集されて横須賀海兵団へ。職業柄、まかない方として重宝された。
働き手を失った一家の生活は苦しいものとなるが、切りつめた暮らしの中から手土産をそろえ、父親を慰問する母についてたびたび海兵団に出かけ、歌った。
兵隊たちもこの口を楽しみにしていた。違い故郷の妻子を想って涙ぐんで聞いていた。父親が戦争へ行く前に終戦、そして復員。
何をしていいか、わからない時代だった。食べるものもなく、ましてや娯楽など皆無であった。
無事帰ってきた父親は仕事のあい間に、近所の青年団とアマチュアバンド「青空楽団」をつくった。
「青空楽団」と「美空ひばり」
もう空襲はない。身に水口をまとっていても、晴れた空に夢をかける。当時の彼らの澄んだ心が伝わって来る。
昭和二十三年五月一日、前年にオープンした野毛国際劇場は、一周年記念特別ショーを開催していた。小唄勝太郎は「童謡の歌える少女に手を引かれて登場したい」と注文を出した。
十一歳の少女が抜擢され、この日、歌手「美空ひばり」がデビューした。舞台を観た人は多い。その印象は観客の胸に強烈に焼きつき、その後に続く栄光の発端として、野毛の街の伝説となった。
時の流れは、この少女に国際劇場の桧舞台に向かって、小さな踏み台を用意した。
その踏み台とは、今は亡き彼女の両親が積み上げた『ダンペ』の箱だったのではないか。そんな気がしてならない。
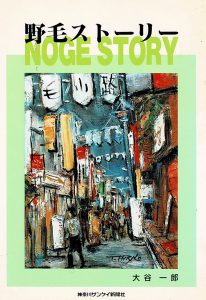 野毛ストーリーより
野毛ストーリーより