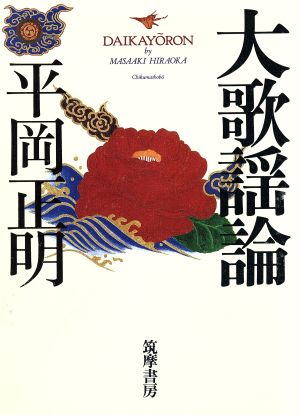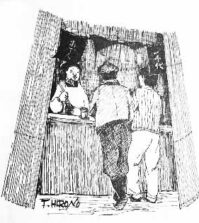大道芸にこそ大衆芸能の原点がある (三波春夫)
皆様も御存知の通り、日本の歌芸は、八百年の昔、藤原澄憲という名僧が始めた「脱経節」から出発しております。
三味線が四百年前に作られて急速に、三味線音楽と歌の完成が進められ、現在の歌舞伎の形になりました。
片や大道を流れ歩く放下師や、大神楽が楽しい大衆芸能を作って参りました。その系列に浪曲や演歌があり、やがて昭和の流行歌、歌謡曲へと移って参りました。
权(さて)
前身は浪曲と云う語り部から出発した三波春夫が、拙ないペンを取って、一文を草しました。
御笑覧願います。
野毛の山からノーエ、ノーエ
野毛のサイサイ
平岡正明さんから「大歌謡論』の初版本を戴いた時、唇をついて出て来た歌である。そもそも歌は、自分が意識して、つまり気に入って覚え、唄いたい。と思うものだがこの歌だけは何時の間にか歌っていた。昭和十九年春。たしか満州で陸軍歩兵の訓練中の事で、日曜日の演芸会の合唱(?)だったと思う。
特に「三島女郎衆はノーエ」の段になると戦友たちは一斉に大きな声を張り上げた。戦友たちは青春の生理現象に関連する問題点に思考力を走らせていたようである。
隣りの戦友は虫歯を押さえて唄っていたのが気の毒だが可笑しかった。
この歌は明治初期に生まれたもので全国に広がった証拠は、歌詞が延々と各地を歌い込んでいると、平岡さんは云う。だからこそ軍隊で盛んに歌われた事になる。
幕末期の「宮さん、宮さん」は品川弥二郎の作詩で日本初の軍歌となったが、詩の内容にはトゲがあって引っ掛かる。考えてみれば日本人同志の争いをテーマとしているから当然の事だろう。
それにくらべると農兵ぶし(ノーエ節)は、人間らしさに溢れている。そして民謡から一歩出て歌謡曲になっているのが、大衆を捲き込んだ要素だと思う。
私は昭和十四年から浪曲家として舞台に立ち、現在まで歌い演じているが、常に新しい創作を続けられたのはありがたい。
すべてお客様という神様のお陰と感謝している。歌手としてすごした三十五年間。
歌は民族の姿である。
歌は民族の心の音である。
と私は思うようになったが、農兵ぶしのように、誰が作り誰が唄い始めたかが忘れられても、大衆の心に遺る歌を創りたい、と思っている。
人々の笑顔を観る倖せ
平岡さんの原稿依頼書に素晴らしいことが書いてあった。
「大道に於いて人々の心を湧かす大衆芸能が成立する場に神が降臨する不思議さ。大勢の人々が集まって芸を観て楽しむ時、大勢の心が一つになる。祭りとなる。それはエネルギーだ。その司祭者は名もなき芸能家であるが、神と人との中に立っているのではないかと思う。神意を感じる野毛の大道芸の凄さ。海を越えて野毛という、いやヨコハマという国際都市を目指す芸人たちの心意気の奥にあるものは何か」
この事について一文を書いてくれとあったが、平岡さんの心の貴さに私は敬意を持つ。
俳聖、松尾芭蕉の言葉に、
貴きを悟りて俗に還るべし。
とあるが、これは人間社会で最も役に立つ訓(ことば)ではないだろうか。
三波春夫の代名詞が「お客様は神さまです」となって久しいが、たしかに私は人々の前で歌う時、人々の歓喜の顔を見る度に私の心は崇まっていく。自分の力を出し切るエネルギーは全身から発散する。この時私はオーラ発光体となっていくのだろう。
若しもお客様が前に居なかったら、こんな心の現象は起こらないのは当然である。
心の昇華。と云えるのだが、野毛の大道でわが芸を披露する機会を与えられた人々は、きっとお客様顔が、その芸を写し出す日本神話の八咫の鏡に見えるだろう。天の岩戸て、ホトを露わにして踊った天細女命(あめのうずめのみこと)の心境と同じになれたら倖せだお客様の、いや多勢の人々の笑顔こそ、神々の心なのだ。
さて、私ことを書いて恐縮だが、どうして芸界に入ったかと云うと、人様の笑顔を見る事が出来るからであった。
私は七才で母に別れた。この悲哀のどん底で父は子供に歌を教へ、共に唱うことに依って救われようとしたのである。
母の仏壇の前で父が歌う「江差追分」を唄いなぞる七才の男の児の歌声は、十万億土の母の魂に届いていたのではないだろうか。
歌は眠明(お経)から始まったというが、文字通り、私の歌の出発は人間の哀しみと対峙していた。
その歌声が歓びと向かい合う時が訪れたのは十才の頃。寿々木米若の浪曲「佐渡情話」を覚えた時からだった。郷土出身の大浪曲家であった米若の節真似は大人たちを非常に喜ばすもので、春の田植えに親族が集まって仕事をする時、私は田園の畦道に立って、知っている限りの歌や浪曲を歌った。腰がズキズキ痛むほどの重労働である田植え作業に、十才の子供が凛と声張り上げて歌う響きは心地良いものだったに違いない。お昼休みには真っ先に私の前に「ぼたもち」の重箱が開かれて、大人たちの嬉しい気持ちが示された。
「俺が歌うと人が歓ぶのだ」
この体験が、東京へ出てから、遂に浪曲の道を歩くようになった。やがて少年浪曲の座長として地方巡行へ。ある時は劇場で。ある時は祭礼の広場で。農家の広間で。何時も一所懸命だった。興行の太夫元は「お前の浪曲はまだ上手ではないがお客が最後まで帰らずに聴いてくれるのは、一所懸命という気迫に客が縛られるんだよ」と言ってくれた。
実は十七才から二十才迄の間、禅僧であった叔父に芸能家としての精神修業を厳しく教えて貰ったのが幸運だった。
座禅の極意は、安易に流れようとする自己の心をコントロール出来る強い意思と教えてくれたが、ある時、私の浪曲を劇場の二階席で聴いていた叔父は、終演後に次の様に問いかけてきた。
「文若よ、今夜お前は客席の何処を見て浪花節を語っていたのかい」
「・・・・・・はい真ん中です」
「すると二階や後ろの席のお客は気の毒だね」
「はあ?」
「お前の目の届かの席のお客様は真ん中の客の半分も喜んでいないんだよ。お前の心は満場のお客様の心を捉えようとしていない。ここが一番大事なところだ。浪花節は「説経節」を源にして出来たものだからこそ、人さまに師匠とか先生とか称ばれる職業だ。それならそれに恥じない勉強をすることだ。本を読め、新聞を開け。人の芸を肥しにするんだぞ。お前が芸と人間を高めてゆけばお客様が喜んでくれる。儂のような坊主より、いい職業だ喃(のう)」
と笑った。
人間の社会に芸能が存在することの意味は限りなく大きいと思うようになったのは、更に私が軍隊。そしてシベリヤの捕虜生活を四年間も味わう事に依って深くなった。
そこには歌と演劇の原点・原型が見えた。
昭和二十年十月に、ロシアのハバロフスクへ連れて行かれたが、私の浪曲が戦友たちにとって心に描く祖国・ふるさとの味だった。勿論私も・・・・・。
やがて歌と音楽のバラエティを演ろうと呼びかけると、それぞれがギターに見立てたホーキを抱えて口三味線。川田晴久の物真似を柱にハバロフスク・ボーイズ(?)ができあがった。
更に芝居を演ろうと提唱したら、参加希望者が益々増えて、企画・演出・主演の私は、稽古稽古で目が廻りそうだった。勿論ステージがある筈はない。収容所の廊下である。喜劇では廊下のすべてを使う演技に、仲間たちの歓声が日曜日の収容所にこだました。ソ連の政治部員は私に注目して、モスクワの劇場へ出演させたいと働きかけて来たが、うまくかわした。その後専門的に芸能集団の指導者になるようにと命令が出たので積極的に務め、これが帰国寸前まで続いた。
ソ連軍と捕虜の関係は勝者と敗者だが人間としては対等であると私は思いつづけたが、それは同時に鋭く政治的な意味を持っていたのである。
作品の内容に当然、主義主張が強く出てはいたが、私は人間として何を想うかが一番大切な事だと信じていた。皆んなの拍手と、涙をこぼして笑う顔。捕虜という極限状態の中で、私は何時しか、
神は人の心の中に住む
と確信するようになったのである。
それは二十年間連続した歌舞伎座の舞台でも、ハウスミュウジックで登場した先日のパワステの舞台※でも変わりはなく、歌と音楽に身をゆだねて楽しむ若い人々の熱狂的な姿に美しい神の心を観るようであった。
自分の技芸を力一杯出し切るには、日頃の鍛練と共に補補を自然に整えて置くことは私どもに最も必要な事と書き加えておく事に致します。
*七月二十三日、新宿花園神社近くのライブスポット「パワーステーション」でロックバンド「電気グルーヴ」をバックに行われた公演。
初出『ハマ野毛 二号』
(1992.6 / 野毛地区街づくり会発行)